雑貨屋のひとり言
もうすぐ74歳になりますが、毎日の生活は気楽で自由です。会社員のときのように束縛されるものがないので家族のこと、自分のやりたいことを最優先にして行動しています。自由ですが朝は早く起きて朝食を食べますし、昼からアルコールを飲むという習慣もありません。お酒は飲みますがアルコール量はちゃんとコントロールできています。リタイア生活は自由なので単調になりがちですが幸い私には「雑貨屋」があり、週末の雑貨屋発行を意識して面白いことがないかアンテナを張るように心がけています。お陰で毎日の小さな変化にも気付けるようになりました。昨年から健康維持のために始めた卓球も週一ペースで楽しくできていて、メリハリのある生活になっています。もう一つ私の住むマンションの役員をさせてもらっているのでご近所が抱える問題や課題に取り組んでいます。わからないことや知らないことが次々にでてくるので勉強の連続です。でもこの取り組みを決して面倒だと思わずに有志の皆さんと正面から受け止め問題解決のために何ができるか考えて行動できていることがとてもいい刺激になっています。近所に皆さんとも仲良く暮らせているのが何よりだと思っています。《R.O.》
川柳(東京・成近)
( 川 柳 )
カラットの自負ケシ粒と言わせない
カラットで呼ばれてみたいガラス玉
カラットの石に漬物石の意地
カラットで計れぬ愛を児に貰い
ダイヤより幸せそうなガラス玉
(ニュースひとりよがり)
「三菱商事撤退」
思わぬ逆風が ―洋上風力発電
「大蛇行終息」
トランプさんもいい加減に ―黒潮
「 石丸代表辞任」
先が見えない ―再生の道
河合成近
龍翁余話(899)「やまなみハイウエイの“ツゲの木アート”」
翁が大分県へ帰省するたびに、必ずドライブするのが『やまなみハイウエイ』だ。大分県湯布院から熊本・阿蘇までの全長約50kmに亘る(大分県・熊本県の)県道11号線は春・夏・秋の3シーズン、くじゅう連山・飯田高原・瀬の本(せのもと)高原の自然が織りなす壮大な景観は、いつ走っても魅力がいっぱい。湯布院盆地のランドマーク的な存在である名山・由布岳(別称“豊後富士”1,583m)を背に『やまなみハイウエイ』を走ると、まずは飯田高原の中心地「長者原」(ちょうじゃばる)に着く。ここは、くじゅう連山の登山口であり、我が国最大級の面積(38ha)を有する大湿原が有名。また環境省長者原ビジターセンターが設けられ、くじゅう連山のジオラマなどの展示やビデオによる阿蘇くじゅう国立公園の紹介などが行なわれている。なお余談だが「くじゅう連山」の名称は、大分県玖珠郡九重町側は「九重連山」、同県直入郡(現・竹田市)久住町は「久住連山」と表記していたが(混乱を避けるため)両町話し合いの末、ひらがな表記になったそうだ。
長者原高原を後に、次なるポイントは『やまなみハイウエイ』で標高の一番高い(1,333m)「牧ノ戸峠」(まきのととうげ)。ここも長者原と同じく「くじゅう連山」への登山口。峠には広い駐車場あり、売店その他の諸施設が完備、『やまなみハイウエイ』ドライバーは、たいていここで小休止。特に6月上旬のミヤマキリシマが咲く頃は、駐車場は早朝から満車だそうだ。もう1つ余談だが1866年(慶応元年)、坂本龍馬が新婚旅行で栗島を訪れた際「山一面を覆う霧島つつじの美しき事」と書いた手紙を姉・乙女に送ったそうだ。また、1909年(明治42年)に、同じく霧島へ新婚旅行に訪れた植物学者・牧野富太郎が、このツツジに感動して「深い山に咲くツツジ」と言う意味で「ミヤマキリシマ」と命名した、と伝えられている。
さて『やまなみハイウエイ』のクライマックスは、見渡す限り大草原が広がる「瀬の本高原」(標高900m)。南には阿蘇五山(高岳・中岳・根子岳・烏帽子岳・杵島岳)、北には「くじゅう連山」を一望出来る。春は新緑、秋には紅葉やススキ、翁がやって来たのは8月のお盆過ぎ、下界は35℃の猛暑だったが、ここは30℃前後の涼しさ。瀬の本レストハウスの“だんご汁”で腹ごしらえをして、いよいよ熊本方面へのドライブ――

「瀬の本高原」から「阿蘇大観峰」方面へ走っていると、突然、道路の左側から目に飛び込んで来た“異様な物体群”、「何だ、これは?」――車20台くらいが停められる広場に翁、車を停めて“異様な物体群”をじっくり眺めると、それは『ツゲの木で作られた動物たちの樹木剪定 アート』だった。1つ1つを観察すると、鶴やキリンなどの動物、恐竜、くまモン(熊本県のマスコットキャラクター)、中には野球選手や力士など数種のオブジェが原っぱ一面に・・・本物の鹿も飼育されており、100円のエサをやると5,6頭の鹿が金網のエサやり場に集まって来る。


駐車場の端に“トウモロコシ売店”がある。焼きトウモロコシ1個(350円)を買い、売り子の女性に話を聴いた。「この公園の広さは約1町(約3000坪)以上あります。これらのオブジェ(ツゲの木を剪定して作られた樹木アート)は、野菜農家兼植木職人の若宮さんと言う人が50年かけて制作したもの」だそうだ。50年前、若宮さんが“千体のオブジェを作ろう”と決意して制作に取り組んだ、だから「千羽鶴」、加えて近隣の山に棲息する野生の鹿を捕獲して飼育し出した、故に『千羽鶴鹿公園』と命名したのであろう(と翁は勝手に推測している)。なお「現在、すでに千体のオブジェが出来上がっている」とのこと。更に(売店の女性の話)「作り方は、成長したツゲ(柘植)の枝を曲げたりして作るのではなく、まず、“作りたいと思う対象をイメージして”ツゲの成長に合わせてワイヤーを使い、枝を曲げながら制作される樹木アート」だそうだ。この売店の女性、かなり詳しいので、“若宮さんの身内の人か”と思ったが確認しなかった。
『樹木アート』は、その名の通り樹木そのものを使用して表現される芸術作品。具体的には「葉っぱの切り絵(リーフアート)」とか「樹木そのものを素材にして作るアート(現代アート)」などあるが、樹木アートは、自然への敬意や樹木がもたらす新しい感性を表現とする手段であるから(翁は)ここ『千羽鶴鹿公園の“ツゲの木アート”』は正に現代アートの典型だろう」と思いながら鑑賞を続けた・・・っと、そこで結ぶか『龍翁余話』。
茶子のスパイス研究「ホームタウン」
こちらLAのサウスベイで過ごす時間も後1ヶ月を切った。長いようであっという間に時間が過ぎた。ここの家主さんはTVは見ないので全て携帯電話からニュースや動画、メッセージを見ている。 なのでこの所、母も私も日本のニュースには頻繁に触れていなかった。それにここの家主は、あまりパソコンを使わないのでWifi の契約を解除し携帯電話の契約に付いているホットスポットのギガを使っている。私もそのホットスポットを利用させてもらっているのでメールのやり取りも不自由なく使えている。 ただ、携帯電話から検索するのはIPad から検索するのとパソコンから検索するのでは画面に限界もあるせいか限られた情報、検索機能の少なさ、手間と時間がかかるという時点では少し不便だ。じっくりあれこれ調べたりするのには、やはりWiiFi 機能のある図書館やカフェでじっくり調べるのがいい。
前置きが長くなってしまったけれど、そんなわけで最近は、あまり日本で何が起きているか把握出来ていなかった。そんな中、数日前に千葉の木更津付近に住む有人から度々メールが入った。
友人は昨年まで学生時代から長く住んでいた東京を離れ千葉の実家に戻った。1番の目的は母親と弟さんの面倒を見る為だ。 私が数年前から頻繁に日本に帰るようになって彼女の友人達と集まっては日本の現状、米国の現状、世界の現状など意見交換をしていた。
初めは私が話す米国の事、海外から見た日本の状況を話してもあまり危機感を感じていなかったように思う。 ふ〜んと聞き流す人もいて実情が伝わらなくて歯痒い思いをしていた。
でも友人も頻繁に田舎に帰るようになり地元の人と話すと隣国から来た人達が井戸のある畑や土地を買い始めた事や勝手に人の家の農作物を 持っていってしまう話など聞かされて心配になったと、、、。
今回の千葉の友人からのメールは深刻だった。日本政府がこっそりとアフリカの政府関係者と密約を結んで いたのがバレて炎上しているのだそうだ。山形県の長井はタンザニア、新潟の三条はガーナ、愛媛の今治はモザンピークそして千葉の友人の住む木更津はナイジェリア、ここが姉妹都市でなく彼らのホームタウンに なるのだそうだ。移民や技能実習生として家族も一緒に受け入れ政府から援助金を出してもらい日本に住まわせ日本をアフリカに献上するわけだ。
政府は誤情報だと大慌てらしいがイギリスのBBC放送もアフリカの公式ページでも発表されているので 誤情報だと言うなら早く日本政府から正式な方法で否定しないと深刻な被害を被る事になる。
そして、この計画を国際協力機構JICA(ジャイカ)が後押しして政府から予算を潤沢に受け取り配るわけだ。
どうも日本政府は海外にお金をばら撒くのが好きなようで自国民には増税、緊縮財政を強いて中小企業虐めをし海外の資本家を太らす事しか考えていなさそうだ。
今年、米国の闇の正体USAIDの実態が暴かれた。その組織とJICAの関係をAIに聞いてみた。以下がその説明だった。
JICAとUSAIDは、開発途上国への支援において、官民連携(PPP)や日米連携プロジェクトを介して協力する関係にあります。JICAが日本の政府開発援助(ODA)として国際協力を実施するのに対し、USAIDはアメリカ合衆国政府の国際開発機関であり、互いの強みを活かして協力することで、より効果的な開発支援を実施しています。
そしてこの組織はCIA の資金や全米民主主義を世界に広める為の教育や資金援助にもなっているそうなのだ。援助や寄付の名目で莫大なお金がいくつもの団体や人を経由してザルのように流れていく実態にようやく日本の若者達が気付き始めた。
スパイス研究家 茶子
追伸:
移民問題に関して今週のエッセイを送った後にてつやさんの大人の社会チャンネル 動画を聞いて驚いてしまいました。
何とアフリカに続いてバングラディシュから10万人の雇用、インドから5万人の移民計画が あってお互いの政府機関で話し合いが行われているようです。
日本で高度な技術習得が目的だとか、、、 今、日本では仕事につけない若者もたくさんいる中でどうして外国からわざわざ高い派遣料を 払って日本の技術をタダで外国に提供しなければならないのでしょうか、、、、
カイロ大学を卒業?したとされている東京都知事はエジプトで仕事に付けない若者を東京都で 働いてもらうプロジェクトも進行中だとか、、、
弱者、貧困ビジネスの裏で公金チューチューしてきたシステムはもう世界でバレバレになって いるのに、今のうちに入れるだけ移民を日本に送り込んでやろうとやる気満々の日本政府です。
スパイス研究家 茶子
小春の気ままな生活 第三十五話 「健康でいる条件・ブラジルの研究」
今週のテネシーは寒気のお陰で、涼しくなりこのまま秋になってしまうのではないかと思うような気候です。先週から、最低気温が摂氏10度前半になるなど、朝晩が涼しくなっています。私がテネシー州に引っ越して来てから、早一年が経とうとしていますが、夏は蒸して暑いよと皆んなに言われましたが、今年の夏はどうやら涼しい方のようで、暑い日もありましたが、外にいて息ができないほどの暑さにはなりませんでした。いつか、暑い日がくるんだろうと思っているこの頃です。
先週の続きですが、今度はブラジルでの研究のお話からです。
コロナで入院している患者で、ICUに入るほどでは無い患者での研究・調査がされたお話です。LED電球で遠赤外線940ナノメートルを発するジャケットを作り、無作為にスイッチを入れた患者と入れない患者で調査したと言います。外からは光が見えないので、患者は自分のジャケットのライトが付いているかどうかはわからないそうです。30人のうち15人はライトが付いていて、他の15人はライトが付いていませんでした。結果は明らかに違く、ライトが付いていた患者は、酸素飽和度(Oxgen Saturation)に進展があり、呼吸を深く出来る様になり強くなっていたそうです。また白血球だけでなく、心拍数や肺動脈拍動数に進展が見られました。驚いた事は入院期間が短かった事です。このジャケットは、毎日(合計7日間)、15分だけ着けていました。LEDライトが付いていなかったグループの平均入院期間は12日であったのに対し、付いていたグループの平均入院期間は8日でした。4日もの差があったそうです。たった30人の結果だったが、信憑性は確かであった為、Dr. Seheultはその後自分の患者は外に出さなければと心に決めていたと言います。ブラジルで使っていたジャケットは売っているものでもなく、自分で作ることもできず患者に着けることはできなかった。ただ、太陽の光は940ナノメーターであることは知っていたので、患者を外に出す事が出来れば病状は良くなるかもしれないと同医師は思ったそうです。そこで、ある患者は、鼻から毎分35Lの酸素を受けていました。コロナのせいで、殆ど浸透していかなく、Dr. Seheultはその患者の担当になり、ゆくゆくは気管挿管しICU行きの患者であった。その時は、そのような患者は何ヶ月ぶりかだったので驚いたが、その患者の病室に言ったらさらに驚愕したそうです。病室はとても暗くて、ブラインドも閉まっていたそうです。娘といたその患者が私に最初に尋ねた事は「先生、僕の余命はどの位ですか?」と。光もなく概日リズム(がいじつリズム:生物の体が地球の約24時間周期の自転に同調して、体温・睡眠・ホルモン分泌など様々な生命活動を周期的に変更させる生体リズムの事です。体内時計とも呼ばれ、このリズムが乱れると睡眠障害や生活習慣病につながる事がります。)がなく、ひどい状態であった。また、その患者は沈んでいた。私は直ちに呼吸療法師と担当ナースを呼び、スタッフのみんな集め伝えた。「この患者を外に出すように。」と。その日は天気の良い日で、太陽が照っていた。呼吸療法師は数本の酸素ボンべを用意し、患者を車椅子に乗せ外に出すことが出来た。
その患者は数週間後に、「先生、私が外に出た初日、とても気持ちが良かったです。」と。この患者は7日間毎日外に出し、初日に35Lから15Lに、そして12L、次の日には8 Lまで下げられました。その後、5Lへと下げることが出来、後5日で酸素なしで自宅へ帰っていったそうです。Dr. Seheultは「勿論もっと大きな調査は必要だが、15〜20分太陽の光に当たる事で良くなるのであれば、やる価値はある。」と話します。
続きは又来週。
小春
ジャズライフ
今週は女性ボーカルを選びました。久しぶりにお気に入りのiFi社のポータブルアンプと有線イヤフォンで聴いて見ました。Halie Lorenの迫力のある音と美しい声のアルバム”After Dark”を選びました。アマチュア無線をしていたときはノイズに埋もれた信号を聞き分けていましたが、高齢になった今、ノイズのない美しい音楽を高性能イヤフォンで楽しめています。
01-After Dark
02-Waters Of March
03-Gray To Grand
04-La Vie En Rose
05-Thirsty
06-Bye Bye Blackbird
07-Ode To Billie Joe
08-Tango Lullaby
09-Beyond The Sea
10-In A Sentimental Mood
11-Happier Than The Morning Sun
12-Give Me One Reason
13-It`s You
14-Time To Say Goodbye
15-Carey
16-I Fall In Love Too Easily
17-My Foolish Heart
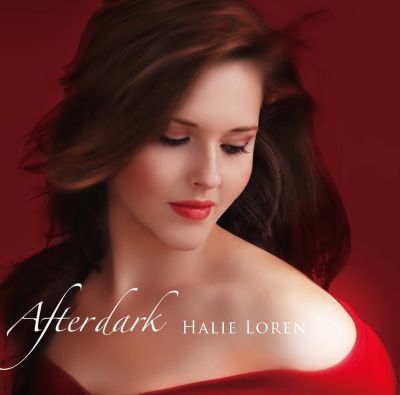
編集後記「オートロックと共連れ侵入について」
オートロック開閉式のマンション玄関で、先に入った住人に追随する形でドアが閉まる寸前に侵入する共連れ侵入で悲惨な事件が神戸市で起きました。この事件を受けてマンションなどでオートロックを採用しているところでの共連れ侵入をどう防ぐかを真剣に考え始めたのではないでしょうか?オートロックは建物に入ろうとする人が持つキーで開けた場合や、インターフォンで部屋の方から遠隔操作で開けてもらった場合だけ入れるので便利なのですが、オートロックでドアが開いた後、ドアが閉まるまでの数秒間に別の人がそのドアに近づくとまた開いてしまうので、故意にそれをされると簡単に建物内に侵入できてしまうのが問題になっています。顔見知りの住民同士ならいいのですが、知らない人にこれをされるときの対応を考える必要があります。
顔を知らない人が共連れで後ろから入ってきた時に「あなたはここの住民ですか?自分のキーで開けて入ってもらえますか?」と言えると理想なのですが、私たち日本人はこういう当たり前のことがなかなか言えないようです。オートロックや防犯カメラでどんなにいいシステムを開発しても、このオートロックシステムを使う住民がもっと意識しないとこの問題は簡単には解決しないように思います。オートロックがある皆さんのところではどのように対応されていますでしょうか?
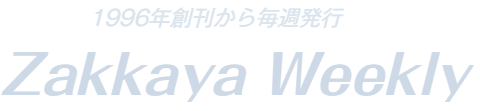



コメント