雑貨屋のひとり言「水道水が飲める日本」
1980年、私が初めてロサンゼルスを訪れた際、水道の水は飲まないようにと言われました。ロサンゼルスの水道水は遠くコロラド川から引かれ、消毒薬が加えられていたため、やや濁っていたように思います。アメリカの会社のカフェテリアでは、コーヒーメーカーの横にあるガラス容器の水を使ってコーヒーを淹れており、飲み水は購入するのが一般的であることを知りました。
当時、日本では水を買うという発想がなく、そのことに大変驚きました。日本では生活インフラが整備され、水道水を安心して飲める環境が整っていたのです。しかし、あれから40年以上が経ち、日本でも生活インフラの老朽化が進み、水道管の漏水事故が全国各地で発生しています。これは、インフラ設備の寿命が近づいていることを示しています。
早急に老朽化対策を実施しなければ、日本も水道水を飲めない国になってしまうかもしれません。ただし、修繕工事によって安価に提供できるかどうかは、設備の整備にかかる費用次第でしょう。その点について国民に理解を促し、国民も納得できるよう努力することが重要だと思います。《R.O.》
川柳(東京・成近)
( 川 柳 )
脇道の花とマイペースが遊ぶ
木も風も空も五月の万歩計
登山靴千恵子の空と風に逢い
一斉にけやき通りが初夏になり
金賞の皐月よ伸びをしたかろう
(ニュースひとりよがり)
「消費減税見送る」
〝消費減、税見送る〟と読んだ ― 国民
「公約に消費税減税」
野党は気楽でいいな ― 赤字国債
「海外制作映画に100%の関税
アメリカ映画専門館に ― トランプ劇場
河合成近
龍翁余話(884)「鯛生(たいお)金山」
大分県日田市から熊本県小国町方面へ走ると、あちこちの脇道に『鯛生金山』の建て看板を見受けるが、翁は『鯛生金山』にはまだ一度も行ったことがなかった。先週号の『龍翁余話』(883)「下筌ダム=蜂の巣城紛争の舞台」の取材地付近にも『鯛生金山』の建て看板が数か所に・・・当日、運転をしてくれた親友S君が「『鯛生金山』はここから近いのでご案内しましょう」と誘ってくれた。本来、翁は高所恐怖症・閉所(狭所)恐怖症なので、タワーや高層ビルの屋上、絶壁など高い所や、洞窟、トンネル、地下室など狭い所はニガ手(しかし、エレベーターやトイレなど日常生活で避けて通れない場所は別)。S君の誘いに一瞬迷ったが、若い頃、取材で「佐渡金山」へ行ったことがあるので“(洞窟の中に入らずとも)概要だけでも学習しようか”という気になって案内して貰うことにした。
「下筌ダム」から「鯛生金山」まで、かなりカーブの多い狭い山道を走る。その間、翁、若い頃に行った「佐渡金山」をおぼろげに思い出していた。新潟県の各地にある金鉱山や銀鉱山をひっくるめて「佐渡金山」と言うそうだが、なかでも「相川(あいかわ)金銀山」の規模が大きく、単に「佐渡金山」と言う場合は「相川」を指す(らしい)。翁が見学した場所も、多分「相川金銀山」だったと思う――「佐渡金山」の歴史は古く、各金銀山の採掘開始時期を調べたら、「西三川(にしみかわ)砂金山」は平安時代、「鶴子(つるし)銀山」と新穂(にいぼ)銀山」は戦国時代、そして「佐渡金山」(いわゆる「相川金銀山」)は江戸時代初期、と記録されている。「金銀山」で働く人(各種鉱物を採掘する人)を「鉱員」(あるいは坑夫、鉱夫)と言うが、江戸時代の「佐渡金山」には、ほかに「水替人足(みずかえにんそく)」と言う労働者がいた。坑道を掘り進むと非常に高い確率で地下水が出る。この水を排出することは極めて苛酷を要するが、鉱山経営では重要な作業だ。「佐渡金山」の「水替人足」は当初は募集により行なわれていたようだが【佐渡金山はこの世の地獄、登る梯子(はしご)はみな剣(つるぎ)】と謳われたように労働環境の過酷さで応募者が激減、そこで江戸幕府は無宿者や犯罪者を強制的に「佐渡金山」へ(水替人足として)送り込むようになった。映画やテレビの時代劇で、そんな場面は沢山観た・・・そんなことを思い出しているうち、S君の車はいよいよ『鯛生金山』へ・・・


『鯛生金山』は大分県日田市中津江村鯛生地区(旧日田郡中津江村)に在る。“金鉱山は、江戸時代以前から”と思い込んでいた翁だったが、ここ『鯛生金山』は1898年(明治31年)から1972年(昭和47年)にかけて(つい125年程前に出来た)比較的新しい金鉱山であったことを知り、驚いた。「佐渡金山」の“手作業”“肉体労働”と異なり、エアー削岩機・火薬・堅杭エレベーターなど近代的な採掘設備を導入し、大規模な採掘によって産出量が増え、最盛期の1934年(昭和9年)から1938年(昭和13年)にかけて、年間産出量は約3トンに及んだ。この時期、全国から約3,000人が集まり、周囲には鉱山町が形成されたそうだ。なお、ここの鉱山は1972年(昭和47年)に資源枯渇のため閉山。稼働年数はわずか74年。記録によると、坑道は地下500mに達し総延長は110kmだそうだ。その後、1983年(昭和58年)4月「地底博物館」開設、2000年(平成12年)8月「道の駅」に登録、2007年11月「近代化産業遺産」に認定されている。
狭所恐怖症の翁がハラを決めて坑道に入った時はすでに午後3時を回っていた(その時間帯の見学者は翁1人)。まず「鉱員を模した人形」に迎えられた。「こんにちは」と言いたいほど精密に出来た人形だ。100mほど奥に入る。掘削作業をしている鉱員(人形)や、当時使われていた各種(新式)採掘設備を見ることが出来た。坑内見学の後「地底博物館」はパス。「砂金採取体験場」を覗いた。大勢の家族連れが砂金取りを楽しんでいた。

急ぎ足の『鯛生金山』見学であったが“佐渡”以来半世紀ぶりの金山見学――悲喜こもごもの人生模様を生んだ“金山採掘労働”ではあったろうが、間違いなく当時の日本経済の基盤を支えた産業であったことは言うまでもない・・・っと、そこで結ぶか『龍翁余話』。
茶子のスパイス研究
LAから移動して今はユタ州で生活をしている友人がいる。昔から植物を育てるのも上手で植物の事を聞けば何でも知っていたし彼女の手にかかると植物が良く育った。植物との相性もあるのかもしれない。植物の状態を感じ取る勘や気配りも他の人よりあり植物に対する感謝や愛情も持ち合わせていた。
友人曰く“ 昔、お爺ちゃんが山に連れて行ってくれて、そこに育つ植物の事をいろいろ教えてもらったから “ そう言った。
幼少の頃に受けた影響は大きいし、それが友人にいい影響を与え学ぶ事が出来たわけで、それこそが人間を育てる教育の一つでもあるのだな〜と、、、。
友人は天然石やクリスタルビーズでアクセサリーを作るのもセンスが良かった。
以前、私にブレスレットを作ってくれた時も私が普段着ている洋服の色を覚えていてその服に合う色のブレスレットだった。
人に何か作ってあげる時は、その人のイメージを考えて作ると言っていた。
天然石の展示会にも良く一緒に出かけた。石の知識も豊富で石の選び方も上手で石の話も彼女が話すと面白く私も天然石に興味を持つようになった。
私がアルバカーキで見つけた石も綺麗にワイヤーで巻きつけてネックレスとして使えるようにしてくれた。

その友人が先日、カゴ網で作ったバッグの写真を送ってくれた。一つ作るのに集中して3〜4日かかると言っていた。だから大量生産された品物とは違う温もりがある。
私も友人がユタ州に本格的に移動する前に白と黒の手作りバッグを頂いた。その手作りのバッグは、たった一つのオリジナル。それがいいのだ。
昔、誰もがこぞってブランド物に憧れ高級なバックが飛ぶように売れた時期があった。いくらヨーロッパの職人さんが丹精込めて作っていると言われても私は全く興味が無かった。
誰もが欲しがる品物が私は欲しくなかったし皆んなが持っているから尚更、私には魅力的には見えなかった。
街では、ブランド物が溢れ、それが一つのステイタスのような所もあった。それに目を付け偽物のブランド商品が隣国から大量に日本に流れ込み輸入商品を取り締まる余計な日本人の仕事も増えた。
その頃、新聞の片隅に浅草でバッグ一筋で仕事をされてきた方の記事を読んだ。もう、かなりのお年だったと思う。その職人さんは仕事用のバッグを作っていた。
その人の要望に応じて書類を入れる場所、お財布などの貴重品やメガネケースを入れる場所も作るのだとか、、、
だから作るのに時間がかかるので予約は数年先だとか書いてあった。その方のモノ作りへの情熱と職人技を知って、この人の作ったバッグが欲しいと初めて思った。
アメリカに行く前の事だったので残念ながらその職人さんに会うチャンスもなかった。友人が送ってくれた手作りのバッグを見て改めてその温もりの良さを感じるこの頃、、、
スパイス研究家 茶子
小春の気ままな生活 第二十話「5月初旬のテネシー」
日本はゴールデンウィークも終わった頃でしょうか、季節もずいぶん変わって暖かくなってきたのかと思います。テネシー州東部は、一週間以上毎日雨マークだったのですが、良く見てみたら、雨は深夜だけだったり、夕立だったり、カリフォルニア州に長い間住んで居たのでなかなか慣れない天気の今日この頃です。雨はよく降り、芝生もグングン伸びてきます。もうそろそろ、庭の芝刈りをしないといけません。また、こんがりと焼けてしまいそうです。
先日、お買い物に行った時に隣にアーミシュの馬車が止まっていました。4月15日が過ぎて、畑仕事をする家庭が多くなってきました。アーミッシュの馬車も苗がいっぱい乗っていました。写真を撮る事ができたので添付しました。また、アーミッシュのマーケットに行った時になんとタケノコが売っていました。細いタケノコで、一本$1.50だったので買ってみました。以前YouTubeで醤油味のタケノコのレシピがあったので、作ってみたらとてもおいしかったです。また後日、同マーケットに行ったら少し大きめのタケノコが一本$2.00で売っていたので、3本買ってきました。この写真も添付します。ここ最近、私の住んでいる近くに3つのアーミッシュマーケットがある事がわかりました。そのうち2つのマーケットに行ったことがありますが、どちらも違うファミリーが経営しているので、お互いの事はよくわからないそうです。私は、一番近い所より私の話によく出てくるTellico Plainsの方が気に入ってます。どちらもとてもいい人ばかりですが、Tellico Plainsの方がとてもフレンドリーな方がいて色々教えてくれます。また、そのマーケットまでは、田舎道でとても綺麗な風景なので、道中も気に入っています。普通のマーケットで買う、ラリッシュ(小粒に刻んであるきゅうりの甘い漬物)が売っており、添加物が使われていないので購入したらとても美味しかったです。アーミッシュマーケットで売れられているから、全てが無添加で良いものだというものではありません。保存料としてCitras Acidを使っていますし、クッキーやパンも売っていますが、シードオイル(キャノラ油など)を使っているので、我が家は買いません。先週Tellico Plainsを訪れた時には野生のターキーを初めて見ることができました。写真添付。地元の方によると、野生のターキーはよく動いているので、足は硬く食べるのは薦めないそうです。アーミッシュの方も忙しくなって来たのでしょうか、以前より町で見かけることが多くなったような気がします。数週間前には、数少ない公衆電話で電話をしていた方もいました。写真添付。アーミッシュの方は、携帯はもちろん、家に固定電話もつけません。電気は使わないので、手動の計算機や軽量機など電気を使わない古いものを使っています。
今週気が付いた事は、道路の脇道に生い茂っている雑草は町の管轄のようで、近所の脇道を一斉に刈って行きました。テネシー州に引っ越してきて初めての年なので、まだまだ初めての経験をしています。アパラチア山脈も緑に生い茂ってきました。我が家はこの夏を上手く過ごせるのでしょうか?追ってご報告したいと思います。
また来週。
小春

ジャズライフ Bob Kindred Quartet “Nights of Boleros and Blues”
今週はBob Kindredのテナーサックスで”Nights of Boleros and Blues”を紹介します。南国ラテンのボレロをブルース・フィーリングでクリエイトされています。メリハリのあるジャズです。《R.O.》
01-Dos Gardenias (Two Gardenias) 《 I. Carrillo 》 (5:36)
02-Que Te Pedi (What I Asked You For) 《 G. Fuente , F . Mullens 》 (6:27)
03-Taboo 《 M. Lecuona 》 (4:44)
04-Toda Una Vida (All My Life) 《 O. Farres 》 (4:27)
05-Angelitos Negros (Little Black Angels) 《 A. E. Blanco, M. A. Maciste 》 (5:01)
06-Obsesion 《 P. Flores 》 (5:34)
07-Alma Con Alma (Soul To Soul) 《 J. Marquez 》 (6:45)
08-Estrellita (Little Star) 《 M. Ponce 》 (5:28)
09-La Comparsa 《 E. Lecuona 》 (2:48)
10-La Mentira (Yellow Days) 《 A. Carrillo 》 (6:20)

編集後記「Ai搭載スマホ」
まだ現用の機種から2年も経っていないのですがスマホを替えました。どこにいても高音質のストリーミングミュージックで新しい楽曲やアルバムを発掘するためにデータ通信量を気にせず聴けるようにしました。新しい機種は嬉しいことに生成AIが使えるようになっているので面白い発見があるかもしれないと期待しています。
新しい機種へのデータ移行は前回同様クイックスタートでやったので比較的簡単にできましたが、アプリやデータが多いせいか1時間以上かかりました。データ転送と言っても古い機種のコピーをしているだけですが、アプリ(特にお金に関わる)によっては引き継ぎ作業があるので注意が必要です。スマホでなんでもできるのは便利なのですが、アプリを入れるたびにIDやパスワードが増えて行くのでスマホを替える予定の方は整理しておいた方がいいと思います。《R.O.》
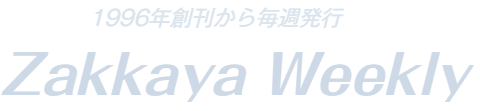



コメント