雑貨屋のひとり言「日本初の女性総裁誕生」
日本初の女性総裁誕生――高市早苗氏のリーダーシップに期待
自民党総裁に高市早苗氏が選ばれ、日本ではじめて女性総裁が誕生しました。正直に言えば、「こうなればいいなあ」と願っていたので、ニュースを聞いた瞬間とても嬉しく感じました。性別にこだわるつもりはありませんが、考え方が明確で、信念を曲げない姿勢に強い好感を持っています。
今回の総裁選では、マスコミが“人気先行型”の候補者を推していましたが、討論会での具体性に欠ける答弁などを見れば、本当にこの国の舵を任せられる人物は誰なのかは自ずと分かるはずです。
高市氏が総裁に就任してから、日本国内だけでなく、海外メディアも即座に「日本初の女性総裁」として大きく報道しました。国際的な注目の高さは、日本にとって大きな転換点になるでしょう。中国や韓国、アメリカなどからもさまざまな反応が寄せられていますが、日本のリーダー像が新しく生まれ変わったことは、世界に鮮烈な印象を与えています。
これからも多くの課題が待ち受けているでしょう。しかし、リーダーが変わることで生まれる前向きな変化に期待しつつ、日本がより良い方向へ進んでいくことを心から願っています。《R.O.》
川柳(東京・成近)
( 川 柳 )
本の帯ほどの知識がよく喋る
憲法を斜め読みして評論家
鬼の首取れず揚げ足ばかり取り
駆け引きの手にジョーカーを持つ強み
期限切れ切り札になおしがみつき
(ニュースひとりよがり)
「靖国参拝見送り」
先ず麻生氏に手を合わせた — 高市新総裁
「26年目の離脱」
あなた私を大事にしなさいよ — 銀婚女房
「坂口さんにノーベル賞」
悔しい — がん細胞
河合成近
龍翁余話(904)「白内障手術」(その2)
10月1日の朝9時、小雨の中、タクシーで旗の台・昭和医大病院の東病棟へ。『老人性初発白内障(右目)手術』のための入院手続きを済ませ、病衣(パジャマ)・タオル類・歯ブラシ(歯磨きチューブとカップ付)のレンタルサービスを申し込んだ後、3階のナースステーション前の待合室へ。ほどなく(担当の)男性看護師がやって来て、翁の病歴や、現在、翁が服用している薬などについての質問、及び入院期間(わずか、3泊4日)の注意事項(説明)のあと、3階諸施設を案内され、いよいよ病室へ。ここで翁、改めて「患者」になったことを意識する。その日は昼メシのあとイヤホーンでテレビと昼寝。6時夕食後にシャワー。明日の手術にそなえ、シャンプーでさっぱりして9時就寝。なお、手術日の3日前から、細菌の感染を抑える目薬を起床時・朝食時・昼食時・就寝前の1日4回の点眼(目薬をさす)を行なっていたので、入院当日も昼食時・夕食時・就寝前に点眼した。
いよいよ手術当日(10月2日)、早朝からさすがに慌ただしかった。手術日の3日前からの細菌感染予防の点眼に引き続いて手術当日の早朝は別の(細菌感染予防の)3種類の点眼薬を与えられた。朝6;30から9;00まで30分ごとの計6回、6:35から9;05まで30分ごとの計6回、6:40から8:40まで1時間ごとの計3回(3種類の)点眼だ。ほかにも体温・血圧・脈拍の測定が行なわれる。これだと、おちおちテレビも見られないし8時の朝食も慌ただしい。9:10に看護師が「手術前の検査があります」ということで翁を呼びに来た。指定された検査室へ。検査の結果「OKです。では手術室で」。看護師が車椅子で翁を「手術室」の前まで運び「頑張って下さい」と言って手術助手に翁を引き渡す。
まず(手術助手によって)血圧計と心電図計がとりつけられる。これは手術終了まで継続。いよいよ(K先生の)「これより水晶体再建手術を行ないます」で開始。目薬のような液体で左右の目の局所麻酔。K先生と助手 の先生の会話は聞こえるが、少し怖くて緊張していたのか2人の話の内容は把握出来なかった。と言うか、翁はすでに“まな板の鯉”(白内障手術の名医・K先生を信頼しての“まな板”)だから2人の先生の会話なんか、どうでもよかった。約20分後「はい、無事終了」のK先生の声は(”まな板の鯉“の)翁にとっては、まさに「神の声」だった。
手術が終わり(手術した右目の)眼帯装着の後、迎えに来た(先ほどの)看護師の車椅子で病室へ。ベッドの上で約2時間安静の後、眼帯がはずされた。入院前に用意しておいた(色の薄い)サングラスをかけ病室を出て、ナースステーション前の待合室から旗の台の街を見下ろす。“お~、遠方がよく見える”翁、思わず声を出した「わ~、綺麗だ!」――
悦に浸っているのも束の間、再び看護師に呼び戻され病床へ。テーブル上にはすでに2種類の点眼薬と点眼表(点眼をする時間指定表)が置かれていた。1つは6:00から3時間ごとの21:00まで。もう1つは6:05から21:05までの(どちらも)1日計6回。手術当日(2日)は12:00から開始。これらの点眼は退院後も医師の指示があるまで継続しなければならない。そのことは(入院する前に)白内障手術経験者の幾人から聞いていたので覚悟はしていたし、術後の目の保護には欠かせない“患者義務”だから、面倒くさがり屋の翁でもこれは真面目に実行するしかない。
ところで、入院時に看護師から渡されていた「クリニカルパス」なるものを読み返した。
「クリニカルパス」と言うのは「特定の疾患や治療に対して、入院から退院までの検査・治療・看護・処置・指導などを時系列でまとめた“診療計画表”」である。これは1980年代にアメリカで開発され、日本では1990年代から普及し始めたそうだ。患者や家族が、入院中の治療スケジュールや退院後の生活の流れを事前に把握し、安心して治療に臨めるための“計画表”である。翁が読み返したのは退院後の“患者の心得”の項である。「起床時からの点眼(医師の指示があるまで継続)の義務」は前述の通りだが、ほかに「眼に水や石鹼が入らないようにシャンプー・洗顔は(退院後5日間は)不可」(10月4日退院の翁の場合は10月9日から可能)。但し、翁は5日間も髪を洗わないのは我慢できない。そこで退院後の2日目に眼帯と保護ゴーグル(メガネ)で目を保護しながら、頭だけにシャワーの湯をかけ、洗髪に成功した。その他の注意事項「重労働や屋外での仕事は医師の指示に従うこと」(翁は、この項に該当する生活はしていないので不要)、「散歩や軽い体操などはいいが水泳やゴルフなど振動の多いスポーツの開始時期も医師の指示に従うこと」。ゴルフ好きの翁、早速、K先生に(翁のゴルフ再開時期を)訊いたらK先生、笑って「10月14日の外来時に(状態を診て)判断しましょう」と言うことになった。
ところで、今回の入院で初めて知ったことだが「入院すると“せん妄”が起こることがある」そうだ。“せん妄”とは、場所や時間を理解する能力(見当識)が低下し、起きていても何となくぼんやりしている(覚醒レベルの異常)状態で、幻覚・妄想などにとらわれて興奮したり錯乱(感情や考えが入り乱れて混乱すること)、活動性の低下といった情緒や気分の異常が突然引き起こされる精神機能の障害だそうだ。その“せん妄”は(若い人でも起こるが)高齢者に多く見られる症状であるとのこと。幸いに翁は、そんな状態にはならなかったが退院後、時計、カレンダーなどは特に気に掛ける、睡眠リズムを(入院以前の通常生活リズムに)早く整える、などの努力をしている。
ともあれ、退院後、1週間を経過しての目の状態は(自己診断だが)実に順調、ただ術後、遠方はよく見えるようになったがパソコンや携帯の文字が見づらくなり、それ用のメガネを用意しなければならなくなったようだ。しかし、白内障手術の目的は「運転免許証取得」と「ゴルフボールの行方確認」だから、それが可能となることを思えば“老眼鏡”ぐらいは――次の左目の手術(10月23日)も頑張ろう・・・と、そこで結ぶか『龍翁余話』。
茶子のスパイス研究「空を仰ぐ」
LA から東京に戻ってきて、そう言えばこの所、空を仰ぐ事が無くなったな〜とふと思った。
空を仰ぎたくても道端でボ〜っと空を眺めていたら自転車や車の往来の邪魔になるし近くの公園に行ってもさほど空の視界は広がらない。
昔はここの2階からも富士山が見えたのだとか祖母が言っていた。もちろん何十年も前の事だから空を遮るほどのビルも少なく住宅街の戸建ても2階建が多かった。今は3階建の家が増え近所にマンションも増えた。
そうなると見える空のスペースも限られて、やはりここは都心の住宅地だった事を自覚させられる。
月が満月になったり欠けていく様を見たり夜明けや夕日の空の色に感動する機会が無いと時間の経過も鈍くなり風情が感じられなくなる。
どこか遠くまで行かなくても身近で瞬く星を見たり雲や空の色が変化していく色彩を楽しめる環境に身を置けたら良いなと思うこの頃、、、
先日、サンペドロのハイキング仲間から今夜の満月は綺麗だったと写真が送られてきた。その時まで中秋の名月の時期もすっかり忘れていた。

“東京には空がない”と言った高村光太郎の妻の言葉。何だかLAの田舎暮らしが長かった私には共感出来る言葉だ。
スパイス研究家 茶子
小春の気ままな生活 第四十話「ご近所さん」
今週のテネシーは気温が少し下がってすっかり秋から冬に向かっている様な感じです。今日の最高気温は摂氏24度、最低気温は13度です。朝晩は大分寒くもうすぐ初霜が降りそうな時期になって来ました。

先週お話しした栗ですが、おいしい栗ご飯が出来ました。レシピはYouTubeで検索し、料理人で和食レストランの賛否両論さんを参考にしました。少し硬めのご飯でしたが、美味しく炊けました。秋刀魚などは手に入らないので、以前冷凍で買ったサバを焼き、お味噌汁も作り和食を作っていただきました。とても満足でした。今回は約10日熟成した栗を調理したので、今度はもう少し待ってみようと思います。もっと甘くなってるといいなと思っています。
今週は別のイタリア人のご近所さんにローズマリーを分けていただいたので、早速フォカッチャを作ってみました。イタリア人だからフォカッチャを作ったのでは無いのですが、週に何度かパンを作るのですが美味しそうなフォカッチャのレシピを見つけてしまったので、オーバーナイトで作ったパン生地を朝出してきて、マフィン型に入れローズマリー・ガーリック・オイルをパン生地につけ15〜20分で焼き上がりました。焼き立てのパンを出かけにご近所さんの家へ寄ってお渡ししました。美味しかったようで、後でお返しにベーコン・ソーセージ(南部スタイル)・豚の顎肉をいただきました。マフィンサイズのパンを4つでこんなに頂いて、とても恐縮してしまいました。このご近所さんとは、食・生活の安全について私と同意される方で、知り合いの酪農農家さんから豚を一頭購入し、お友達と半分こしたそうです。私の住んでいる町では酪農農家さんが沢山いるので、牛を直接購入して冷凍庫に入れている人が沢山います。また、庭も広いので玉ねぎ・人蔘・トマト・きゅうり・バターナッツスクワッシュなど収穫したものを瓶詰めにし、地下室に保管してその年の食料にします。我が家はガーデニングまで手が届きませんでしたが、少しずつ増やしていこうと思います。我が家でたった一つできたのは、偶然できたスイカです。現在季節外れにグングン育っていて、明日くらいに収穫しようかと思っています。このスイカは前の家主さんがスイカを食べたときに、ぺっと吐いた種が育ったようです。
そんなことで、テネシーの田舎はとてものどかで、近所付き合いもとても盛んです。学ぶ事も多く、主人とまるで外国に引っ越して来たみたいだねと話します。
また来週。
小春
宇山和夫「あだ名(NickName)」
今日は、あだ名はどんなふうに付けられるのか? 興味半分でAIに聞いてみた。
Quote
『あだ名の付け方は、相手の特徴、趣味、性格などを反映させたり、親しみを込めた響きにしたりするのが一般的です。名前の一部を略したり、「〜ちゃん」、「〜くん」、「〜さん」といった敬称を付けたり、呼びやすい言葉を選ぶことも大切です。ただし、相手が嫌がらないよう、相手の性格や関係性に配慮し、事前に確認するか相手の反応を見ながら適切な呼び方を見つけることが重要です』
Unquote
これは特に日本国内における判断基準とまでは行かないまでも、あだ名の付け方における指標、アイデアみたいな、一般的な当たり障りのないアドバイスだろう。周りが認めた上で、また、本人も了承の上で決まるものなのだろうと思う。だから、本人の前で言えない、ある特定のグループの中で蔓延る特定の人を狙ったあだ名は正確にはあだ名(Nickname)とは言えない。悪意を込めてしまうとパワハラにもなりかねない。
一方、日本人が外国で生きてゆく場合、例えば米国で生活をする場合、結構あだ名が重要だ。アメリカ人が発音をしやすい様に本来の日本の名前を削ったり短くする必要が出てくる。例えば、知人で、そのまま好きな俳優の名前を使った人もいた。 James Deanが好きな彼は自分の名前との関連性をもたせないで勝手に James Komatsu とか名乗っている。 例えばMikioさんならMickyとなりえるし、譲二さんだったら 正にGeorge そのままで良い。 女性の場合、尚美だったらユダヤ人の名前でNaomiがあるので、これもそのままで良い。
大学を出て最初に務めた印刷会社の初代ロス所長の福田さんの名前は知行、Tomoyukiだった。シラブル(音節)が4つもあるので 削ってTom(Thomasの略)にしたらしいが、これはスッキリ納得できる。余談になるが福田さんは大いに頑張ってGeorgetown Univ.を必死で卒業しており、指にはいつもご自慢の大学の指輪が光ってた。その印刷会社としての私は2代目だったが、米国駐在になる前の25歳の時だったが、福田さんに連れられて米国中に散らばる顧客群を片っ端から巡業させて頂いた事がある。その時、若かりし私にあだ名(Nickname)はなかった。テネシー州のメンフィスのお客様の前で福田さんが私のことを日本からのJohn Denverと紹介した。(カラオケの私の18番)
『貴男を何と呼べばいいの?』とメンフィスのお客さんが聞く。福田さんが咄嗟に和夫(宇山)は音節が3つで長いから Kazie(カジー)にしようとなり、1977年の夏にGod Fatherを福田さんとして米国テネシー州メンフィスでKazie が産声を上げた。 それ以来、50年近く、私は Kazie のままである。命名して頂いた福田さんは東京のサイマル Internationalで教鞭を取っていた時に亡くなられたと奥様から聞いた。 過労死。55前の若い死だった。私は今のKazieであることに福田さんに感謝を捧げたい。
宇山和夫
ジャズライフ Tingvall Trio “Birds”
ピアノとベースによる軽快なリズムが特徴の楽曲”Woodpecker”から始まるピアノ・トリオTingvall Trioのアルバム”Birds”を紹介します。 Tingvall Trioは、スウェーデン出身のピアニストMartin Tingvall、キューバ出身のベーシストOmar Rodriguez Calvo、ドイツ出身のドラマーJürgen Spiegelによる、国際色豊かなピアノトリオです。《R.O.》
01-Woodpecker
02-Africa
03-SOS
04-The Day After
05-Air Guitar
06-Birds
07-Birds of Paradise
08-The Return
09-Nuthatch
10-Humming Bird
11-Nighttime
12-A Call for Peace

編集後記 「2025関西万博閉幕」
4月13日に開幕した関西・大阪万博が、いよいよ明日で閉幕します。 開幕当初はマスコミがネガティブな報道をしていたこともあり、しばらく様子を見ていましたが、5月に南夫妻から「一緒に大阪へ行きましょう」と声をかけていただいたのをきっかけに、思い切って通期パスを購入しました。
酷暑だった7月・8月の来場は避けたため、結局、通ったのは全部で7回ほど。それでも回を重ねるごとに入場者が増えていくのがよくわかりました。
最後の万博をしっかり目に焼き付けようと、先週6日と8日の2回訪れました。9月中旬に予約していましたが、どちらも夕方17時からの入場です。先月13日に行ったときと比べるとずいぶん涼しく、入場待ちの列も苦になりませんでした。
6日の日は天皇陛下がご訪問されていたようですが、それに関係なく会場はたいへんな人出で、歩くのも一苦労でした。東ゲートから入場したのは16時頃。パビリオンの予約はなかったので、まずは大屋根リングに上がると、ちょうど空飛ぶ車のデモ飛行を見ることができました。その後、会場の西の端まで歩いて、瀬戸内海に沈む夕陽を眺め、あたりが暗くなる頃には「中秋の名月」が西ゲート付近の空に美しく浮かんでいました。

そして、最後の訪問となった10月8日は、万博を締めくくる大きな花火と、初めての「ドローンショー」を存分に楽しみました。

55年前、大阪・千里の万博会場で見た「ワイヤレス電話機」が、今では多機能スマートフォンへと進化したように——。
きっと次の時代には、空飛ぶ自動車が当たり前のように空を行き交う日が来るのだろうなあと思いながら、会場を後にしました。 《R.O.》
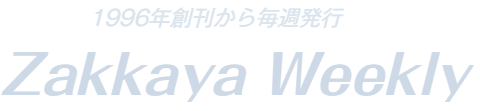



コメント