|
�����]�b�i131�j�u�ۂ̓��E�O�H�ꍆ�فi���p�فj�v
�F�l�i�ǎҁj��������u���T�A�G�b�Z�C�w�]�b�x�������̂͑�ςł��傤�v�Ɠ����邱�Ƃ��悭����B�������Ǝ��̂͂���قǂł��Ȃ����A�l�^�i�e�[�}�j���l���A�T���̂͐����A���Ȃ荜�܂�B�����Ƃ╶���l�A�X�|�[�c�l�E�|�\�l����꓁���f�ɂ���̂������͂Ȃ����A�Ⴂ������̃h�L�������^���[�f������̏K���ŁA�o���邾�������̑��Ō���ɏo�����A�h�����āE���āE�m���߂āg��S�����A���H�������C�����͎R�X�B�������G�l���M�[���܂��c���Ă���̂Ɋ̐S�̃e�[�}��������̂���ρB����ȉ��ɓ�����Ă����F�l��������A���܂ɁA�q���g��^���ĖႤ���Ƃ�����B���łɁw�]�ˏ�����Ɏc�������T�K�x�A�w�����X�J�C�c���[�̌��Ɖe�x�A�w�����j�Տ���x�A�w�쒹�ώ@�x�ȂǁA���̋����S�������䂭�A�C�f�A�����������Ă���̂ō���Ɂh������ҁg�Ɛ\���グ�Ă����������A������A���p�ُ��肪�D���Ȑe�F�EJ����u�ۂ̓��E�O�H�ꍆ�فi���p�فj�ցw�}�l�ƃ��_���E�p���W�x���ςɍs�����v�Ƃ̃��[���Ղ����B�O�H�ꍆ�ق͍��N4��6���ɐ����I�[�v����������B���A�G����ԃ����K�̌������̕����D���ŁA���������ɍs���Ă݂����Ǝv���Ă����̂����AJ����ɐ���z����Ă��܂����B
������23���ŃX�^�[�g������̓h���}�w���n�`�x�A�ŋ߂�18�����������Œ�����Ă���B�j���Ƃ͈قȂ���b�̑����Ɏ����҂����C�������Ă����̂��낤�B���������̂Ƃ�����j�w�ҁi���n�����ҁj��S���́h���n��g����͉��̃N���[�������Ă��Ȃ��B���A���̂��Ƃ͂�����w�]�b�x�řႦ�����Ǝv���Ă��邪�A����͂��Ă����A�����ۂ̓���т́A���̃h���}�̋������E���푾�Y�i�O�H�����̑n�Ǝҁj���ېV��ɐ����ƂȂ��A�]�ˏ�i�c���j�ɋ߂����喼���~��сi�ۂ̓��j�ɖڂ����A�����y���ˏo�g�̖����V���{�̏d���E�㓡�ۓ�Y��_�ޏ���̃o�b�N�A�b�v�Ĕ��������݂��B�������A���̒n�ɂ͗��R�Ȃ◤�R�֘A�{�݂��������̂Ŗ푾�Y�������͎������Ȃ������B�ނ̎��i����18�N�j��A��V���i�푾�Y�̒큁2��ڎВ��j�A�v��i�푾�Y�̒��j��3��ڎВ��j�̎��X�Ȑ��E�H�삪����t���Ė���23�N�Ɋ��Ƃɕ����������A�푾�Y�̖��͂��Ɍ����ƂȂ�A���̈�сi�ۂ̓��A�����g�O�H�P���h�ƌĂꂽ�j���ߑ�r�W�l�X�X�ɕϖe�������B
�@
 |
 |
| �c���O�L�ꂩ�猩���ۂ̓��r���Q |
�O�H�ꍆ�ق̐��� |
�O�H�ꍆ�ق̌��݂�1894�N�i����27�N�j�A�p���̌��z�ƃR���h���i����H�w�����z�w�ȏ��㋳���j�̃f�U�C���ɂ��B���ꂩ��110�]�N�o���āA�����̌�����������A�v�}��ʐ^�����ƂɁA230���̃����K��������đS������E�l���W�ߎ葢��ŕ��������Ƃ����B
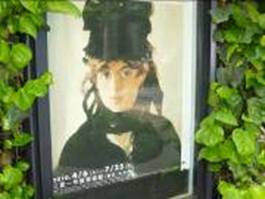 |
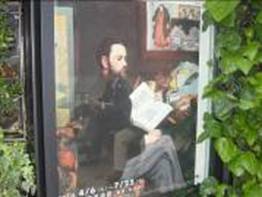 |
| �x���g�E�����]�̏ё��i���j�ƃG�~�[���E�]���̏ё��i�E�j����������O�ɓW������Ă���ʐ^�@ |
���͖{���A���p�ɂ͂���قǂ̋��������w���[���Ȃ��B�������R�ɂ��A�G�h�E�A�[���E�}�l�Ɣނ̍�i�̊���͒m���Ă���B20���N�O�I���Z�[���p�فi�p���j�Łw�V���y�t�i�҉��y�t�j�x�ɏo������̂��ŏ��B�c�O�Ȃ���A���̊G�͊O�ɂȂ������̂ŎB�e�͏o���Ȃ������B
�@
����������B20���I�̃C�M���X�|�p�E���\���钤���ƃw�����[�E���[�A�i1898�N�`1986�N�j�̍�i�g�����̃u�����Y�g�����w�҂����|����B���̒���̑O�ɐ����̃J�t�F��������ׂ�B������Ƃ����p���̊X�p�̕��͋C�B�R�[�q�[�ł��A�Ǝv�������i�����Ƃ����̂Ɂj�ǂ̓X�����ȁB4��6���̊J�وȗ��i�J�Î����j36���ڂœ��َ҂�10���l�����������B�����I�ɂ͐e�FJ��������̒��̈�l��������������Ȃ��B�����w�ۂ̓��o��������H�ɉ����ėL�y�����ʂ֕�����5���A�����̂ǐ^�Ɉʒu����w�O�H�ꍆ�فx�́A�����̖����������A�O��A�Z�F�Ɏ������{�̎O������ɂ̂��オ�������t�@�~���[��痂������������łȂ��A�����E�|�p�̍����Y�킹�h��s��̃I�A�V�X�g�Ƃ��Ă̌e���ƈ��炬�������o���Ă��邱�Ƃ��S�n�����B�����p���̃R�[�q�[���E�E�E���ƁA�����Ō��Ԃ��w�����]�b�x�B |